
新築のマイホームなのに、トイレや排水口から下水臭がする。せっかくの新居での生活が、予想外の臭いトラブルで台無しになってしまうのは大変心配なことです。
下水臭の原因は「封水切れ」や「排水トラップの不具合」「施工ミス」など様々です。
本記事では、水道メンテナンスセンターの現場責任者として数多くの新築住宅の臭気トラブルに対応してきた経験から、臭いの原因と効果的な対策法、そして施工業者との交渉術まで徹底解説します。
DIYで解決できるケースと専門家に依頼すべきケースの見極め方も含め、新築住宅での下水臭問題を根本から解決するための実践的な知識をお伝えします。
トイレつまりでお困りの場合、水道メンテナンスセンターが解決策をご提供します。疑問や懸念については、電話、メール、LINEでの初期相談も可能です。
トイレの水漏れトラブル税込2,200円~ 年間施工実績1000件突破!
この記事のポイントは?
新築なのにトイレや排水口から下水臭がする原因

新築住宅なのに突然トイレや排水口から下水臭がするのは、主に以下が原因です。
- 封水切れ
- 排水トラップの構造と不具合
- 施工ミスや換気設計の問題
- 便器周辺のシーリング不良
- 一階の排水経路特有の臭気問題
- 洗面所・風呂からの逆流臭
- 排水システムの初期不良
封水切れとは?下水臭発生の最も多い原因
封水切れは、新築住宅で下水臭が発生する最も一般的な原因です。排水口には「封水」と呼ばれる水のバリアがあり、これが下水管からの臭気を家の中に逆流させないための重要な役割を果たしています。
引っ越し直後の新築住宅では、日常的に水を使っていない排水口の封水が自然蒸発してしまうことがよくあります。特に使用頻度の低い洗面所の排水口や来客用トイレなどは要注意です。
排水トラップの構造と不具合
排水トラップは下水臭を防ぐための重要な設備ですが、新築住宅でもその構造や設置に問題があると臭気の原因となります。
排水トラップには「P型」「S型」「U型」など複数の形状があり、それぞれ設置場所に適した形状が選ばれます。しかし、施工時に適切なトラップが選ばれていなかったり、取り付け角度に問題があったりすると、本来の封水機能が十分に発揮されません。
よくある不具合としては、トラップ内に「溜まり水」ができづらい設置角度になっていたり、配管の接続部分に微細な隙間があり、そこから臭気が漏れ出すケースがあります。
また、新築時の検査では水を流して漏水がないことは確認されますが、臭気の漏れについては十分な検査が行われないこともあります。専門業者による「臭気センサー検査」などで正確に診断することが重要です。
施工ミスや換気設計の問題が引き起こす臭気
新築住宅での下水臭は、単なる封水切れだけでなく、施工段階でのミスや換気設計の問題に起因するケースも少なくありません。
「通気管(ベントパイプ)」の設計・施工不良は深刻な臭気問題を引き起こします。しかし、通気管の口径が小さすぎたり、配置が不適切だったりすると、排水時に管内で負圧が生じ、封水が吸い込まれて「サイホン現象」が起きてしまうのです。
換気設計の問題も見逃せません。浴室や洗面所の換気扇を強く回すと、室内が負圧になり、排水口の封水を通して下水から臭気を引き込むことがあります。特に気密性の高い新築住宅では、この現象が起きやすくなっています。
「一般建築物排水設備基準」では適切な通気管の設置や配管の勾配が定められていますが、施工時のわずかなズレが原因で基準を満たしていないケースもあります。
便器周辺のシーリング不良による臭い漏れ
便器周辺からの下水臭は、見落とされがちな「シーリング不良」が大きな原因となっています。
トイレの便器は床に固定される際、便器底部と床面の間に特殊なシーリング材やワックス製の「ワックスリング」が使用されます。これらは便器からの排水が床下に漏れないようにするだけでなく、下水管からの臭気が室内に逆流するのを防ぐ役割も果たしています。
新築住宅では、このシーリング材の施工が不完全だったり、便器の固定が不十分だったりすると、微細な隙間から下水臭が漏れ出します。
実際の現場では、便器設置時の「フレキ管接続部」の接続不良も多く見られます。トイレの排水管と便器をつなぐフレキシブルな管の接続部分が緩んでいたり、パッキンが適切に機能していなかったりすると、そこから臭気が漏れ出します。
便器周辺のシーリング不良は、専門業者による「漏水検査」で発見できますが、新築時の検査では見逃されることも少なくありません。
一階の排水経路特有の臭気問題
一階のトイレや排水口は、建物の排水経路の特性から、上階とは異なる臭気問題を抱えることがあります。
一階の排水設備は、直接「屋外桝(外部排水マス)」につながっているため、屋外の臭気が室内に逆流しやすい構造になっています。特に「雨水・汚水合流方式」を採用している地域では、大雨の後などに下水管内の圧力が高まり、臭気が逆流することがあります。
また、一階の排水管は比較的短いため、排水の勢いが強く、トラップ内の封水が不安定になりやすいという特徴があります。排水時の水流が強すぎると、封水が一部流されてしまい、「部分的な封水切れ」が生じることもあるのです。
さらに、庭や外構工事で設置された「屋外排水桝」の設計や施工にも注意が必要です。桝の蓋が適切に閉まっていなかったり、桝内部の仕切りに問題があったりすると、そこから臭気が漏れ、風向きによっては室内に入り込むことがあります。
一階特有の臭気問題は、建物周辺の排水設備全体を点検する必要があり、単に室内の配管だけを調べても原因が特定できないことが多いのです。
洗面所・風呂からの逆流臭の可能性
トイレだけでなく、洗面所や風呂場からも下水臭が発生することがあり、これには特有の原因が存在します。
洗面台や浴室の排水口は、髪の毛や石鹸カスなどの汚れが蓄積しやすく、これらが腐敗すると独特の臭いを発生させます。新築住宅でも、施工時の配管内部に残った切削屑や接着剤などが、使用開始後に汚れと結合して臭気の原因となることがあります。
また、洗面所や浴室の排水管は複雑な経路をたどることが多く、「排水勾配」が不十分だと、管内に汚水が滞留して臭気を発生させます。
新築マンションの場合、入居後しばらくは全戸が使用していない状態があり、排水管内の微生物バランスが整っていないことも臭気の一因となります。
築浅でも起こる排水システムの初期不良とは
新築住宅といえども、排水システムに「初期不良」が発生することは珍しくありません。むしろ、使用開始直後だからこそ表面化する問題もあるのです。
建築現場では、排水管の接続試験として「満水試験」や「気密試験」が行われますが、これらは短時間での漏水の有無を確認するものであり、微細な不具合や長期的な使用を想定した検査ではありません。
そのため、実際の生活で水を使い始めると、これまで気づかなかった問題が表面化することがあります。
新築住宅で特に多いのが「配管内部の異物」です。施工時に配管内に入り込んだセメントの破片や配管の切れ端、さらには作業員が誤って落とした小物などが、徐々に水の流れを妨げ、排水不良や臭気の原因となります。
新築住宅の排水システムの初期不良は、施工業者の責任範囲となるケースが多いです。
新築住宅でできるトイレ下水臭対策と改善方法

新築住宅での下水臭は、適切な対策を講じることで改善できます。早期発見・早期対応が、快適な住環境を取り戻す鍵となります。
封水切れの正しい補水方法
下水臭の主な原因である「封水切れ」は、適切な確認と補水で比較的簡単に解決できる問題です。
まず、封水切れの確認方法ですが、排水口に懐中電灯を当てて覗き込み、水面が見えるかどうかをチェックします。トイレの便器の場合は、便器内の水位が通常より明らかに低くなっていないか確認しましょう。
封水の補水は、単に水を流すだけでは不十分なケースがあります。特に長期間使用していない排水口では、排水管内の乾燥によって水が素早く流れ去ってしまうことがあります。
正しい補水方法は以下の通りです。
- 排水口に栓をし、水をためる
- 約5分間水を溜めたままにする
- 栓を抜いて水を流す
- 再度少量の水(コップ1杯程度)を静かに流し入れる
特に注意すべきは、使用頻度の低い排水口です。来客用トイレや季節によって使用頻度が変わる洗面所などは、週に1回程度、意識的に水を流す習慣をつけることで封水切れを防げます。
排水口・排水トラップの清掃と消臭方法
排水口や排水トラップの汚れも、下水臭の原因となります。適切な清掃と消臭で臭いを大幅に軽減できます。
まず基本的な清掃方法として、排水口の目皿やトラップを取り外し、溜まった髪の毛や汚れを除去します。新築でも施工時のゴミが残っていることがあるため、入居後の初期清掃は特に重要です。
清掃後の消臭には、市販の排水管用洗浄剤も効果的ですが、新築住宅ではまず以下の方法を試してみましょう:
- 40℃程度のお湯を静かに流し、配管内の油脂類を溶かす
- 重曹200gとクエン酸100gを混ぜ、排水口に投入して5分後に水で流す
- 台所用漂白剤を薄めて流す(※塩素系とアルカリ性の洗剤は混ぜないこと)
特に効果的なのが「定期的な温水流し」です。週に一度、40〜50℃程度のお湯を各排水口に流すことで、配管内の汚れを徐々に溶かし、臭気の発生を抑えることができます。
防臭キャップや専用グッズの活用方法
施工業者による根本的な解決を待つ間や、一時的な対策として、防臭グッズの活用は非常に効果的です。
まず代表的なのが「防臭キャップ」です。これは排水口に取り付けるゴム製のキャップで、普段は閉じていて水を流す際に水圧で開く仕組みになっています。
特に使用頻度の低い排水口に取り付けることで、封水が切れても臭気の逆流を防げます。
また、「ワントラップ」と呼ばれる後付け可能な排水トラップも有効です。既存の排水口に追加設置することで、二重の封水効果が得られます。
特に浅い封水しかない排水口には有効な対策となります。
臭気が便器周辺から漏れている場合は、「便器固定ボルト」の増し締めが効果的なことがあります。便器の両側にあるキャップを外し、固定ボルトを適度に締め直すことで、便器と床の間の隙間を減らせます。
ただし、過度な締め付けは便器を破損させる恐れがあるため、注意が必要です。
施工業者への確認ポイントとチェック方法
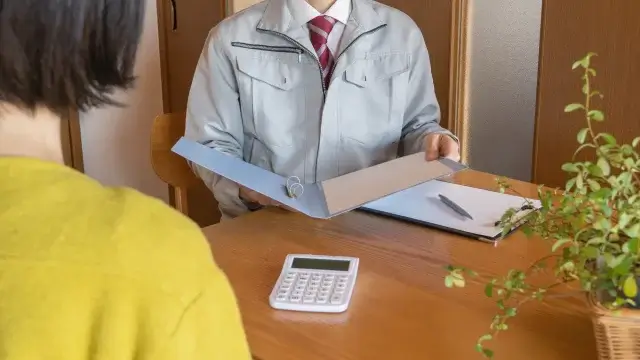
下水臭の原因が施工不良にある場合は、建築会社や施工業者への確認が必要です。効果的な確認のためのポイントをご紹介します。
確認し記録しておくポイント
まず、臭いが発生する場所と時間帯を具体的に記録しておきましょう。「朝方にトイレから臭う」「お風呂の使用後に洗面所で臭いが強くなる」など、パターンを把握しておくことで、原因特定が容易になります。
施工業者に連絡する際は、以下の点を確認してもらいましょう。
- 排水管の勾配が適切か(標準は1/100)
- 通気管(ベントパイプ)の設置位置と口径は正しいか
- 各排水トラップの形状と設置状態は適切か
- 配管接続部のシーリングに問題はないか
- 屋外桝との接続状態に異常はないか
施工図面と実際の施工状態を比較してもらうことも重要です。図面通りに施工されていない場合や、現場での判断で変更された箇所がある場合は、その影響を確認する必要があります。
臭気テストの実施依頼
また、「臭気テスト」を依頼するのも効果的です。これは、特殊な発煙剤を排水管に流し、煙の漏れを確認するテストです。
目に見えない臭気の漏れ箇所を視覚化できるため、問題箇所の特定が容易になります。
多くの場合、新築住宅の設備には1〜2年の保証期間があり、この期間内であれば無償修理の対象となることが多いです。
新築の下水臭トラブルの費用負担は?建築会社との交渉術

新築住宅での下水臭トラブルは、基本的に施工会社の責任範囲です。引き渡し後の保証期間内であれば無償対応されるケースが多く、適切な交渉と対応により、費用負担なく問題解決できる可能性があります。
引き渡し直後の不具合は「施工会社の責任」が基本
新築住宅の引き渡し直後に発生する下水臭などの不具合は、基本的に施工会社の責任となります。通常の使用で発生した排水設備の不具合は、施工会社が修理すべき「瑕疵(かし)」に該当するのです。
ただし、引き渡し時の「瑕疵担保責任期間」は契約によって異なります。一般的には建物の構造部分は10年、設備関係は1〜2年程度とされていることが多いですが、契約書の内容を確認することが重要です。
施工会社に連絡する際は、以下の点を明確に伝えましょう。
- 問題が発生している具体的な場所と症状
- いつから症状が現れているか
- どのような状況で臭いが強くなるか
- すでに自分で試した対処法(もしあれば)
また、連絡は電話だけでなく、メールやFAXなど記録に残る方法で行うことをおすすめします。「○月○日に電話で伝えたにも関わらず対応がない」という事態を避けるためです。
保証期間内なら無償対応されるケースが多い
新築住宅の設備不良は、保証期間内であれば無償で修理されるケースが多いです。
新築住宅の設備には通常、「アフターサービス保証」または「瑕疵担保保証」が設定されています。排水設備のような機能部分は、一般的に引き渡し後1〜2年の保証期間が設けられていることが多いでしょう。
この期間内に発生した不具合は、基本的に無償修理の対象となります。ただし、以下のようなケースは保証対象外となることもあるため注意が必要です。
- 入居者の使用方法が原因でのつまりや不具合
- 経年劣化による封水トラップのゴムパッキンの劣化
- 入居者が行った改修工事が原因の不具合
保証を受ける際は、「設備保証書」や「住宅設備機器保証書」などの書類を用意し、購入時の契約内容と照らし合わせることが重要です。
ハウスメーカーとのやり取りで注意すべき点
ハウスメーカーとの交渉は、適切な対応を引き出すための重要なステップです。効果的なコミュニケーションのポイントをご紹介します。
まず、問題を伝える際は感情的にならず、具体的な事実を時系列で説明することが重要です。「いつ、どこで、どのような臭いがするか」を明確に伝え、可能であれば写真や動画で状況を記録しておきましょう。
担当者との会話は可能な限り記録に残しておくことをおすすめします。メールやFAXなどの書面でのやり取りが理想的ですが、電話の場合は会話の要点をメモし、後日「○月○日の電話では~と伝えました」と確認のメールを送るなどの工夫が有効です。
また、初回の連絡で適切な対応が得られない場合は、担当者の上司や別の窓口に相談することも検討しましょう。
ユーザー責任と言われた場合
注意すべきは、ハウスメーカー側から「使用方法の問題」と言われるケースです。
例えば「清掃不足」や「排水口への異物混入」など、居住者側の責任を示唆されることがあります。このような場合でも冷静に、以下のような反論が効果的です。
- 「新築入居直後から発生しており、使用方法に問題はありません」
- 「他の同様の排水口では問題が発生していません」
- 「専門書やメーカーの取扱説明書に従った使用をしています」
一方で、ハウスメーカーとの良好な関係を維持することも重要です。将来的なメンテナンスやリフォームのことを考えると、過度に対立的な姿勢は避け、問題解決を共に目指す姿勢で交渉することをおすすめします。
施工業者が費用負担を拒否した場合の対応策
施工業者が費用負担を拒否するケースも残念ながら存在します。そのような場合の効果的な対応策をご紹介します。
拒否に対する対応策としては以下の方法があります。
| 対応策 | 注意点 |
|---|---|
| 第三者による調査・診断の実施 | 専門の診断業者や建築士に依頼して調査を行います。 調査費用は5〜10万円程度かかりますが、問題解決のための投資と考えましょう。 |
| 行政機関への相談 | 地方自治体の住宅相談窓口や消費生活センターに相談することも有効です。 |
| 住宅専門の紛争解決機関の利用 | 「住宅リフォーム・紛争処理支援センター」や「建設工事紛争審査会」などの専門機関に相談する |
| 内容証明郵便の送付 | 問題点と要求事項を明記した内容証明郵便を送付 |
| SNSや口コミサイトの活用 | 最終手段です。事実関係を正確に伝え、感情的な表現は避けるべきでしょう。 大手ハウスメーカーには効果的な場合があります。 |
また、費用負担の「部分的な妥協案」を提案することも解決策の一つです。例えば「材料費は施工業者、工賃は折半」といった提案は、交渉の糸口になることがあります。
重要なのは、すべての交渉内容と経過を記録に残しておくことです。
水道修理業者に依頼すべきタイミングと費用相場を知っておこう
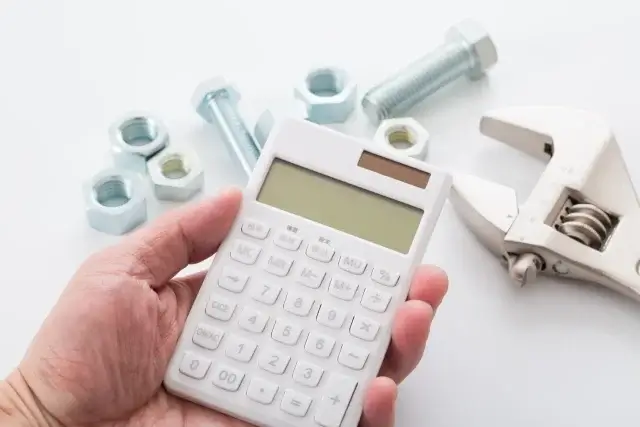
下水臭問題は自力で解決できるケースもありますが、原因によっては専門業者に依頼することが最適な選択となります。
DIYでは対応できない症状の見極め方
下水臭の中には、専門知識や特殊な道具がなければ対応できない症状があります。DIYの限界を知り、適切なタイミングで業者に依頼することが重要です。
以下のような症状が見られる場合は、DIY対応の限界と考えるべきでしょう。
| 業者に依頼すべき症状 | DIYでは治らない理由 |
|---|---|
| 複数の排水口から同時に臭いがする | 建物全体の排水システムや通気管に問題がある可能性が高く、専門的な診断が必要 |
| 水を流すと「ゴボゴボ」と音がして臭いが強くなる | 排水管内で「負圧」が発生している証拠で、通気管の問題や配管のつまりが考えられます |
| 床下や壁からの臭い | 配管の破損や接続部の劣化が考えられます |
| 臭気が季節や天候に関係なく常に存在する | 築から間もない時期に発生する持続的な臭いは、施工不良を疑うべき |
| DIY対策を試みたが、短期間で再発する | 専門業者による根本解決が結果的に経済的 |
業者に依頼する前に行っておきたいのが「臭いの記録」です。いつ、どこで、どのような条件で臭いが強くなるかを記録しておくと、業者の診断が正確になります。
例えば「朝方に強くなる」「雨の後に発生する」「お風呂を使った後に洗面所で臭う」といった情報は非常に有用です。
最終的に、不安があれば早めに相談することをおすすめします。無料の現地調査を行ってくれる業者も多いので、まずは相談から始めてみましょう。
排水設備の再施工・改修の平均費用
排水設備の問題を専門業者に依頼する場合の費用相場を知っておくことで、適正な予算計画が立てやすくなります。
| 工事種類 | 費用目安 |
|---|---|
| 排水トラップの修理(部品交換のみ) | 5,000〜15,000円 |
| 排水トラップの交換 | 15,000〜30,000円 |
| 排水管接続部のシーリング修理 | 10,000〜20,000円 |
| 排水管の部分交換(1m程度) | 20,000〜40,000円 |
| 通気管の修理 | 15,000〜30,000円 |
| 新規通気管の設置 | 30,000〜80,000円 |
| 便器周りの再シーリング(シーリングのみ) | 10,000〜20,000円 |
| 便器周りの再シーリング(便器取り外し・再設置を含む) | 20,000〜40,000円 |
| トイレ周りの配管やり直し | 80,000〜150,000円 |
| 浴室・洗面所の排水管再施工 | 100,000〜200,000円 |
| 建物全体の排水システム改修 | 300,000円〜 |
これらはあくまで一般的な相場であり、建物の構造や使用材料、地域によって変動します。
また、見積もり内容には、以下の項目が含まれているかを確認しましょう。
- 材料費・部品代
- 人件費・作業料
- 出張費・交通費
- 廃材処理費
- 保証内容と期間
複数の業者から見積もりを取ることで、適正価格の把握と技術力の比較ができます。
ただし、極端に安い見積もりには注意が必要です。中には適当な応急処置だけで終わらせる業者もあるため、工事内容と使用部材を詳細に確認することが重要です。
尼崎市水道修理税込2,200円~ 年間施工実績1000件突破!
まとめ
新築住宅でトイレや排水口から下水臭がするのは、封水切れや排水トラップの不具合、施工ミスなど様々な原因が考えられます。特に引っ越し直後は配管内の水量バランスが安定していないため、臭気が発生しやすい状態にあります。
構造的な問題がある場合は専門家の力が必要です。新築の場合、保証期間内なら施工会社の責任で無償修理されるケースが多いため、症状を詳しく記録して早めに連絡しましょう。
DIYでの対応が難しいと判断したら、弊社「水道メンテナンスセンター」を含む複数の専門業者から見積もりを取り、適切な修理方法を選択することが大切です。下水臭の問題は放置すると生活の質を大きく下げるだけでなく、健康面でも悪影響を及ぼす可能性があります。
適切な対策で快適な住環境を取り戻し、大切な住まいで安心して暮らせるようにしましょう。
よくある質問
新築で入居したばかりなのにトイレが急に下水臭くなりました。まず何をすべきですか?
改善しない場合は、施工不良の可能性もあるため、新築であれば建築会社やハウスメーカーに連絡することをおすすめします。保証期間内であれば無償で対応してもらえるケースが多いです。
当社「水道メンテナンスセンター」でも初期相談は無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
下水臭の原因を特定するためにプロに調査を依頼したいのですが、費用相場はどれくらいですか?
基本的な目視点検:5,000〜10,000円
臭気センサーによる検査:15,000〜30,000円
配管内部のカメラ調査:20,000〜40,000円
煙試験(スモークテスト):30,000〜50,000円
ただし、調査費用は以下の状況で変動することがあります:
地域による料金差
建物の構造や規模
調査範囲の広さ
弊社「水道メンテナンスセンター」を含む多くの業者では初回の簡易調査を無料で行っています。新築住宅の場合は、まず施工会社に相談し、保証対象かどうかを確認することが重要ですが、第三者の専門家の意見を聞くことで問題解決が早まることも多いです。
